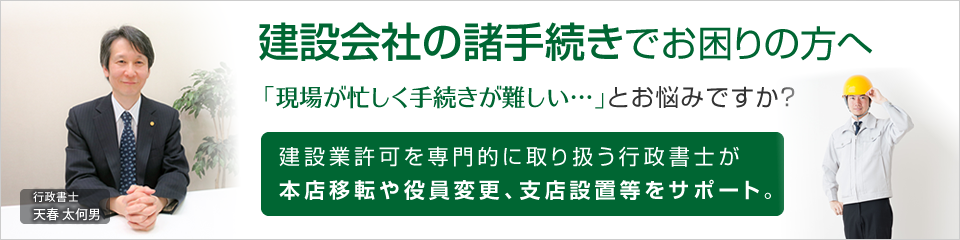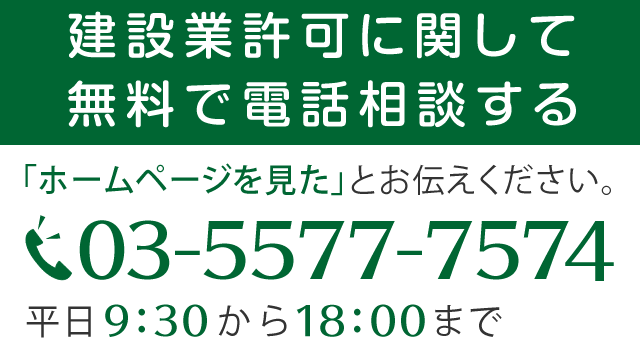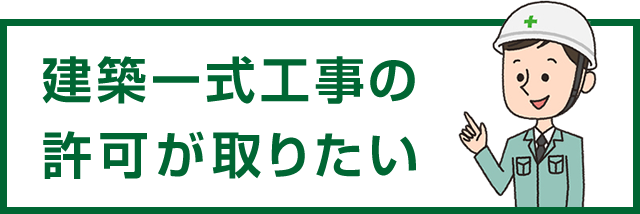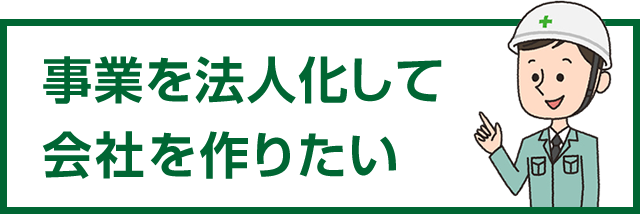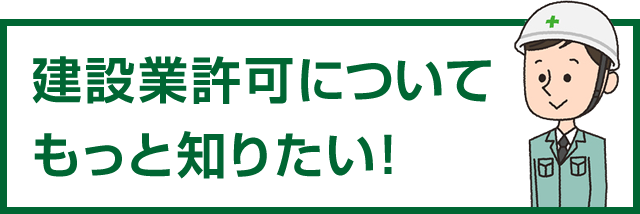- 外国人の役員の場合、何か特別な手続きがあるの
- 外国人の役員が就任した際に、必要となる添付書類って何・・・
- 外国人の役員の場合、書類の記入どうすれば良いの・・・
建設会社の中には、外国資本の参画によって外国人の役員(取締役)を迎えられるケースが増えています。
また、外国人の方が日本で建設会社を経営され、役員(取締役)の中に、複数の外国人の役員(取締役)がいらっしゃる場合もあります。
外国人の役員を就任させた場合の添付書類
建設業許可の新規取得や継続には、常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)を常勤で置かなければなりませせん。
従って、建設業許可の新規取得や継続のため、外国資本や外国人経営の建設会社であっても常勤役員等(経営業務の管理責任者(経管)等)や専任技術者(専技)は日本人である場合もあります。
そのようなケースでは、外国資本や外国人経営者は、非常勤の役員(取締役)に就任され、通常は、母国にて経営を統括されているようです。
また、建設会社様の中には、外国人の役員(取締役)を迎えた場合、日本人とは異なる建設業許可上の特別な手続があるかご心配される方がいらっしゃいます。
確かに、外国人の役員(取締役)の場合でも日本人の役員(取締役)と同じ提出書類で良いのか不安になられるのも当然と言えます。
日本に住まれていない外国人を非常勤の役員(取締役)にされるわけです、添付書類の取得や書類の記入には神経質にならざるを得ないと思います。
役員に就任した際の必要となる添付書類
役員に就任された際には、役員毎に申請書に添付しなければならない以下の提出書類があります。
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明書)
- 身分証明書(破産者で復権を得ないもの等に該当しない旨の区市町村長の証明書)
これらの添付書類は、外国人の役員(取締役)でも取得しなければならない書類なのでしょうか。

「登記されていないことの証明書」については外国人の役員(取締役)も取得しなければなりません。
「登記されていないことの証明書」は、法務局で取得できます。
注意点としては、外国人の役員(取締役)は、本籍地ではなく、国籍を記載しなければならないということです。
また、住所も、記載できるのは日本における住所地となるので、外国在住の役員(取締役)の住所欄は空欄となります。
尚、日本人(日本国籍)の場合、通常は住民票上の住所となります。
では、「身分証明書」についてはどうでしょうか。
「身分証明書」は、本籍地の各市区町村の戸籍事務担当課で発行されます。
外国人の役員(取締役)は、日本国籍を持たれていません。
従って、外国人の役員(取締役)には「身分証明書」を発行できません。
つまり、外国人の役員(取締役)は「身分証明書」は必要ないのです。
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
また、外国人の役員(取締役)も申請書の添付書類として「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」(様式第十二号)を提出しなければなりません。
住所については、外国人の役員(取締役)が外国に住まれている場合でも、そのお住いの外国の住所を記載します。
そして、法人の場合には、当然、役員(取締役)個人の氏名を記入します。
外国人の役員(取締役)も例外ではありません。
外国人の役員を就任させた場合の添付書類(まとめ)
外国人の役員(取締役)を就任させた場合の申請書への添付書類についてご説明してきました。
具体的には、「登記されていないことの証明書」と「許可申請者の住所、生年月日等に関する調書」について取り上げてきました。
これらの書類は、建設業許可申請や変更届の手続を行う際には、必要となる大切な添付書類です。
申請や届出に取り組む前に、少しでも不安や心配は取り除いておきたいものです。
弊事務所では、建設業許可申請について、人的・組織滝・物的・財産的基礎要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出代行と手続全般をサポートしています。
建設業許可申請でお悩みの建設業者様は、お気軽にご相談ください。
行政書士に建設業許可取得を依頼する場合
行政書士に建設業許可申請をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなります。
ご依頼の流れ
建設業許可申請をご希望される場合のご依頼の流れとなっています。
| お客さま | お電話・メールにて相談をご予約ください。 |
| 行政書士 | 建設業許可申請のご相談をいたします。 |
| お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、建設業許可申請を代行させていただく際の料金目安となります。
| 許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
|---|---|---|---|
| 知事許可 | 一般 | 国家資格 | 150,000円~ |
| 実務経験 | 180,000円~ | ||
| 特定 | 200,000円~ | ||
| 大臣許可 | 一般・特定 | 250,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、建設業許可の取得に必要な諸費用となっています。
| 許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
|---|---|---|---|
| 知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
| 大臣許可 | - | 150,000円 | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を原則的に出張相談でお受けしております。
この初回出張相談は無料となっております。