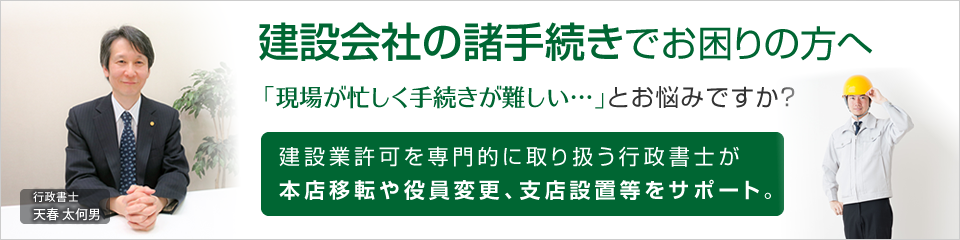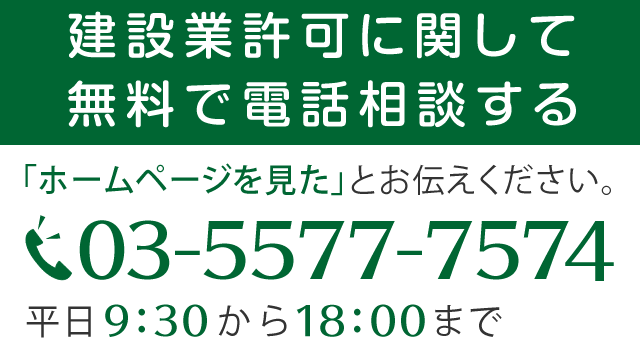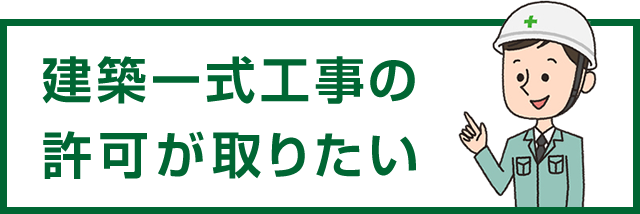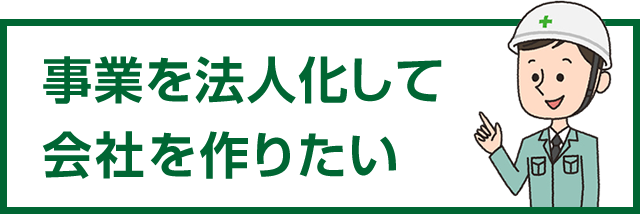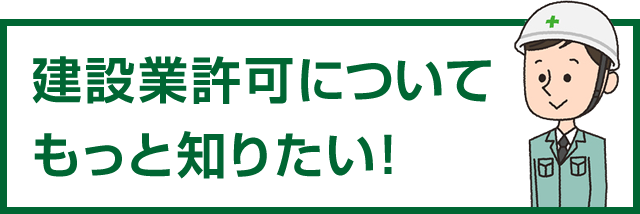- うちの場合は、社会保険の適用事業所にあたるの
- 個人事業主ならば、社会保険は関係ないよね・・・
- 一人親方から法人化したけど、社会保険は何か変わるの・・・
社会保険加入の建設業許可の要件化
令和2年10月1日の建設業法改正によって、社会保険への加入が建設業許可の許可要件になっています。
社会保険の適用が除外される場合を除き、社会保険への加入が確認できないと、新規・業種追加・更新申請等の許可申請や承継等の認可申請を行なえません。
既に建設業許可を取得されている社会保険未加入の建設業者様の場合は、未加入のまま令和2年10月1日以降に建設業許可の申請を行うと建設業許可の取り消しとなってしまいます。
そこで、社会保険未加入のため建設業許可を取得できない、維持できないといった事態に陥らないよう、また、工事を受注できない、作業員が現場に入ることができないといった事態にならないよう、社会保険について、その仕組みを理解しておく必要があります。
建設業における社会保険
通常、社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことを言っています。
ただ、建設業の社会保険未加入対策における社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険のことを意味しています。
従って、次段では、その3つの保険の適用対象について説明するとともに、建設業特有の労災保険について説明いたします。
健康保険と厚生年金保険について
<事業所の形態から>
- 常時使用される者が5人未満の個人事業所 ⇒非適用事業所(国民健康保険・国民年金等に加入)
- 法人事業所もしくは常時使用される者が5人以上の個人事業所 ⇒適用事業所
従業員5人未満の個人事業所については適用事業所ではありません。
従って、その場合には、法的に社会保険未加入で問題になることはありません。
<適用事業所で働いている人の属性から>
- 法人代表者、役員(常勤)⇒強制適用
- 個人事業主とその家族従業員 ⇒適用除外(国民健康保険・国民年金等)
- 常用労働者 ⇒強制適用
- 常用労働者以外の短時間労働者 ⇒適用除外(国民健康保険・国民年金等)
- 季節労働者等 ⇒適用除外(国民健康保険・国民年金等)
たとえ、法人代表者おひとりであったとしても、法人の場合には、強制適用となります(法人代表者は、健康保険と厚生年金保険に加入義務あり)。
雇用保険について
<就労者の属性から>
- 事業主、代表者、役員 ⇒加入不可
- 労働者 ⇒強制適用
- 65歳以上、学生、生徒等 ⇒加入不可
1人でも労働者を雇っている事業主は、法人事業か個人事業かを問わず、一部例外を除いて加入手続を取らなければなりません。
被保険者は、1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある者となっています。
尚、雇用保険は、法人の役員や個人事業主とその家族は加入できません。
但し、法人の役員や個人事業主の家族で、労働者としての身分を有しており、従業員給与を支給されている場合には、例外的に加入できることがあります。
建設業の労災保険 について
オフィス等事務所で働く方のための労災保険については、営業所ごとに一般継続事業の労災保険に加入することになります。
他方、現場の労災保険については、元請会社が下請会社の分も含めて適用事業所として現場の労災保険に加入します。
これは元請業者の義務であり、下請工事のみ取り扱う事業者の場合には、現場の労災保険の保険料はかからないことになります。
事業主(役員)、代表者、一人親方の現場労災について
但し、元請会社の労災保険の適用範囲は、元請会社の社員(労働者)や下請会社の社員(労働者)のみとなっています。
従って、事業主(役員)、代表者、一人親方、家族従業員については、別途、特別加入の手続を取る必要があります(労働者災害補償保険特別加入)。
その際には、労働保険事務組合に事務を委託する必要があるので、注意を必要とします。
建設業と社会保険について(まとめ)
社会保険未加入の建設業者様の全てが悪意で社会保険に加入していないわけではないと考えております。
と言うのも、社会保険に加入したいとお考えの建設業者様であっても、余りに保険料の負担が大きく、保険料の支払いで事業の利益が全てなくなってしまう、と躊躇されることも多いからです。
ただ、国土交通省は、社会保険の適用事業所については加入率100%を目指しており、この方針は変わることはないでしょう。
従って、建設業者様が指導を受け、その際に保険料の支払いが難しい場合、その旨を年金事務所や労働局に相談してください。
社会保険に未加入のままでは、建設業許可の取得や維持ができず、また、経営事項審査(経審)の大幅減点、工事現場への入場拒否、下請業者としての取引先から除外されることにもなりかねません。
更に、強制加入の手続きが取られた場合、以前から事業の実態があったと判断されると、適用が最大過去2年遡り、過去2年分の保険料を徴収されることもあります。
中央省庁や地方公共団体の入札参加希望者、ゼネコンの下請業者、許可業者にとどまらず建設業者様にとっては、まさに、社会保険の加入は待ったなしの状況と言えます。
ここまで、建設業と社会保険について、社会保険制度の大枠についてご説明させていただきました。
更に、詳しいご説明や具体的な手続や保険料についてご相談のある方には、弊事務所より建設業専門の社会保険労務士事務所をご紹介させていただきます。
また、建設会社設立や建設業許可の取得の際に、社会保険加入をご検討の方にも建設業専門の社会保険労務士事務所をご紹介させていただきます(希望者の方)。
兵事務所では、建設業許可に関する申請書や変更届について、建設業者様に代わって申請や届出を行っております(代行申請)。
建設業許可に関する申請書や変更届でお悩みの建設業者様は、お気軽にお問い合わせください。