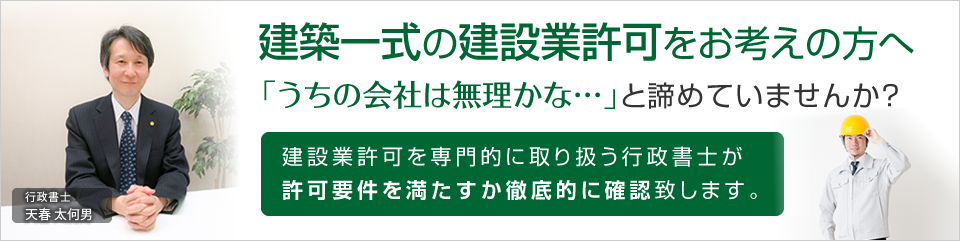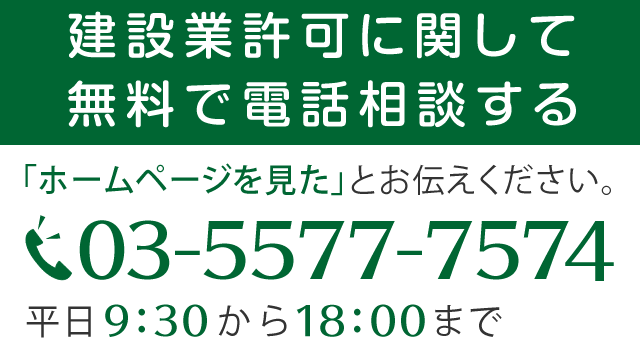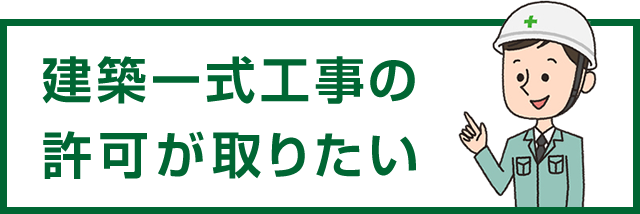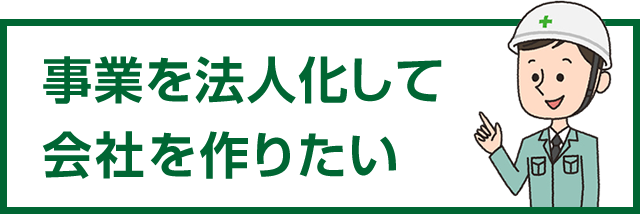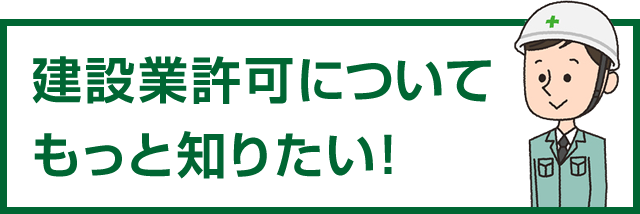- 「営業所」に常勤役員等(経管)と営業所技術者等(専技)を置けば、後は何も気にしなくとも良いね
- 物理的な事務所スペースさえあれば、建設業許可上の「営業所」として認められるよね・・・
- 建設業許可上の「営業所」と認められるためには、何を注意しなければならないの・・・
建築一式工事の建設業許可を取得するためには、建設業許可取得の前提として「営業所」の設置を必要としています。
建設業者様の中には、建設業許可上の「営業所」として認められるための要件について、余り気にされていない方も沢山いらっしゃいます。
建築一式工事の「営業所」要件
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)もいる、営業所技術者等(専任技術者)も準備した、お金もあるので大丈夫だ(財産的要件)、事務所は自宅を使う。
こんな感じに考えておられる建設業者様、注意してください。
建設業許可上の営業所の設置を安易に考えていると、他の建設業許可の要件を全て充たしていても建設業許可を認めてもらえないこともあるのです。
そこで、本記事では、そんな残念な事態にならないよう建設業許可上の「営業所」の要件を確認していきます。
また、建設業許可上の「営業所」の設置における注意事項についても詳しくご説明いたします。
建設業許可の要件を充たした事務所を整備して、許可行政庁(国土交通大臣(各地方整備局長)や都道府県知事)に建設業法上の「営業所」と認めてもらえるように準備しましょう。
そして、建築一式工事の建設業許可の取得をより確実なものとしましょう。
先ずは、建設業法体系が想定している建設業許可上の「営業所」の意味について確認していきます。
建設業法体系上の「営業所」
建設業許可上の「営業所」とは、「本店または支店」もしくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。
「本店または支店」の注意点としては、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でなくとも、本店または支店で、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、建設業法上の営業所に当たるという点です。
この判断を間違うと、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の設置、営業所技術者等(専任技術者)の営業所への設置、建設業法施工規則第3条の使用人の営業所への設置、建設業許可を申請する許可行政庁(国土交通大臣(各地方整備局長)や都道府県知事)等を間違ってしまう可能性もあります。
なお、建設業を他の事業と兼業する場合の支店や営業所で、建設業に全く関係ない事務所や単に登記簿上の本店に過ぎないものは、ここでいう「営業所」には当たりません。
また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積・入札・契約締結等請負契約の締結に係る実質的な行為を行う事務所のことを言っています。
従って、必ずしもその事務所の代表者が契約上の名義人となっているかは問われていません。
つまり、請負契約書の名義人がその事務所の代表者の名義でなくとも、その事務所で請負契約の見積・入札・契約締結等請負契約の締結に係る実質的な行為を行っている場合、その事務所は「営業所」に当たることになります。
なお、建設業に関係のある事務所でも特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所や作業所、単なる事務連絡所は「営業所」には該当しません。
建設業許可上の「営業所」に当たるか否かの判断は、その事務所で行っている行為の実態に応じて行われることになります。
そして、「営業所」の最低限の要件として、例えば、次のような要件を備えていなければならないと考えられています。
<最低限の要件>
◎契約締結に関する権限を委任されており
◎事務所などの建設業の営業を行うべき場所を有し
◎電話、机等の什器備品を備えており
◎看板・標識等で建設業の営業所であることを外部から認識できる表示のあること
なお、建設業許可上の「営業所」の所在地とその営業に係る建設工事の施工場所については、建設業法は特に制限していません。
つまり、「営業所」の所在する都道府県の区域以外の地域においても、その「営業所」で締結した請負契約に基づいて建設工事を施工できます。
次に、建設業許可上の「営業所」として備えるべき要件について詳しく確認していきます。
建設業許可上の「営業所」の要件
建設業法上の「営業所」は、一般的には次のような要件を備えなければならないと考えられています。
ちなみに東京都都市整備局市街地建築部建設業課発行の「建設業許可申請・変更の手引」にこの要件は詳細に記載されております。
<営業所の要件(参考:東京都)>
- 外部から来客を迎え入れ、建設業の請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
- 建設業の請負契約の締結等ができるスペースを有し、他法人または他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること(独立性が保たれていること)
- 個人の住宅である場合には居住部分と適切に区分されているなど独立性が保たれていること
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)または建設業に関する「経営体制(常勤役員等と常勤役員等の直接補佐者)」、建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
- 営業所技術者等(専任技術者)が常勤していること
- 営業用事務所としての使用権限を有していること
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
なお、営業用事務所としての使用権限を有していることとは、自己所有の建物か、賃貸借契約を締結していることを言っています。
また、住居専用契約の場合、原則として建設業許可上の「営業所」として認められません。
建設業法施行令第3条に規定する使用人(通称 令3条の使用人)とは、建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者を言います。
建設業許可上の「営業所」の設置における注意事項
<使用権原・事務所形態>
例えば、都営住宅、UR都市開発機構、JKK住宅供給公社等の公的賃貸住宅の物件は、原則として建設業許可上の「営業所」とは認められません。
ただし、貸主の承諾を得ることができる場合、許可行政庁(国土交通大臣(各地方整備局長)や都道府県知事)によっては相談に応じてくれることもあるようです。
これらの物件の事務所を建設業許可上の「営業所」とお考えの建設業者様は、許可行政庁(国土交通大臣(各地方整備局長)や都道府県知事)と必ず事前に相談しておく必要があります。
いわゆるレンタルオフィスも建設業許可上の「営業所」として認められない可能性があります。
これについても、審査行政庁によっては、例えば2年以上の賃貸借契約を締結し、他の法人と明確に区分されている等を条件に相談に応じてくれることもあります。
レンタルオフィスについても許可行政庁(国土交通大臣(各地方整備局長)や都道府県知事)と必ず事前相談しておく必要があります。
なお、フリーロケーションのオフィスやバーチャルオフィスについては建設業許可上の「営業所」としては認められないと考えてください。
また、個人の住宅を事務所とする場合、建設業の執務スペース(事務所スペース)とその他居住スペースを明確に区分しておく必要があります。
例えば、リビング等の居住スペースを通らないと建設業の執務スペース(事務所スペース)に行けない場合、建設業許可上の「営業所」の要件を充たしているとは判断されません。
従って、個人住宅を事務所にする場合、建設業の執務スペース(事務所スペース)と居住スペースとの区分をどうやって実現するかを考えておく必要があります。
仮に、部屋の間取りの制約上、どうしても建設業の執務スペース(事務所スペース)と居住スペースを区分できない場合には、外に事務所を借りることも検討しなければなりません。
また、個人住宅を事務所とする場合、住宅の見取図や間取図の提出を求める許可行政庁(国土交通大臣(各地方整備局長)や都道府県知事)もあります。
<明確な区分・独立性>
ここで「区分」について補足説明いたします。
執務スペース(事務スペース)と他のスペースを区分しようとパーテーションの設置を検討されるケースがあります。
このパーテーションの設置についても注意を必要とします。
つまり、パーテーションが簡単に移動できる場合には、執務スペース(事務所スペース)とその他のスペースを明確に区分していると判断されないのです。
これについては、法人様であっても個人様であっても同じ扱いとなります。
法人様の場合、他の法人様と執務スペース(事務所スペース)をシェアーしている物件では特に注意しなければなりません。
更に、簡単に移動できないパーテーションであっても背の低いものは駄目で、背の高いものを用意する必要もあります。
近年、建設業許可上の「営業所」の要件の中でも、「明確な区分」や「独立性」については、より厳しく判断される傾向が強くなっています。
<必要なもの・什器類>
建設業許可上の「営業所」に必要なものや什器類として、例えば、電話機、コピー機、FAX機、PC、机、椅子、来客用テーブル、来客用椅子等を挙げられます。
これらについても細かい注意を必要とします。
例えば、電話機については、許可行政庁(国土交通大臣(各地方整備局長)や都道府県知事)によっては携帯電話を不可とするところもあります。
今まで携帯電話でお仕事をされていた建設業者様は、固定電話を用意しなければなりません。
携帯電話の取り扱いにも、許可行政庁(国土交通大臣(各地方整備局長)や都道府県知事)に事前確認しておく必要があります。
また、許可行政庁によっては、机や椅子の数についても、従業員数との数の整合性を指摘されることもあります。
従いまして、来客用の椅子やテーブルについても執務用や従業員用のものとは別にご準備いただく方が許可行政庁(国土交通大臣(各地方整備局長)や都道府県知事)の指摘を避けられると思います。

建築一式工事の「営業所」要件(まとめ)
ここまで建築一式工事を含む建設業許可上の「営業所」の要件について確認してきました。
また、建設業許可上の「営業所」の要件を挙げるだけではなく、実際の審査において指摘され得る注意事項についても詳しくご説明しております。
実際の建設業許可上の「営業所」の要件確認では、今回の記事の他に営業所写真等の確認によって更に厳しく判断されることになります。
「営業所」の写真撮影ひとつをとっても、建物の全景・事務所の入口・事務所の内部と細かく撮影を求められます。
更に、国土交通大臣許可では、営業所現地調査にも力を入れています。
これらを見ても、「営業所」の設置は、建設業許可の取得において重要な意味を持っていることを表しています。
建築一式工事の取得を新規申請でお考えの建設業者様は、建設業許可上の「営業所」の設置についても万全の準備をお願いいたします。
それでも建設業許可上の「営業所」の要件について、良くわからないとお困りのお建設業者様は、建設業専門の弊事務所までお気軽にお問い合わせください。
弊事務所では、建築一式工事を含む建設業許可申請において、建設業許可要件の確認、各種証明書類等の収集、申請書の作成、審査行政庁への提出と手続全般を代行しております。
建築一式工事を希望される建設業者様、建設業許可申請の代行について、弊事務所に一度相談してみませんか。