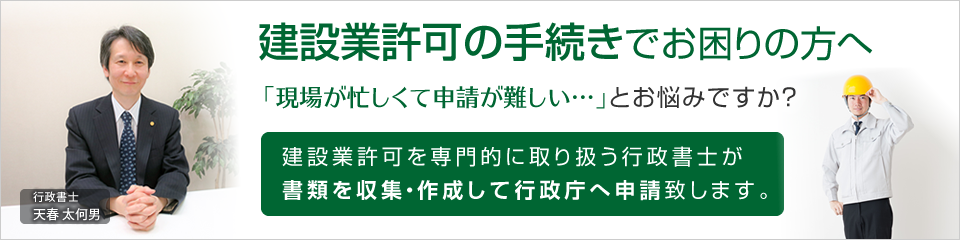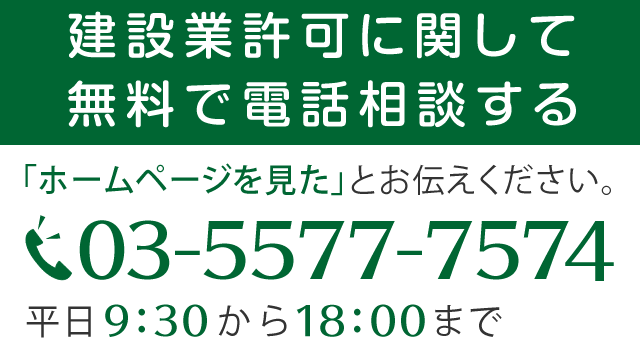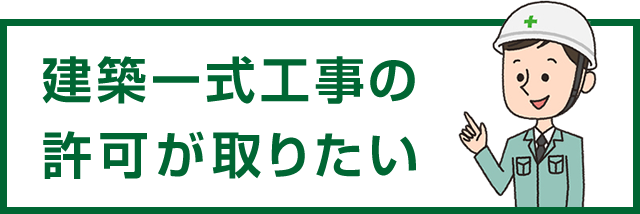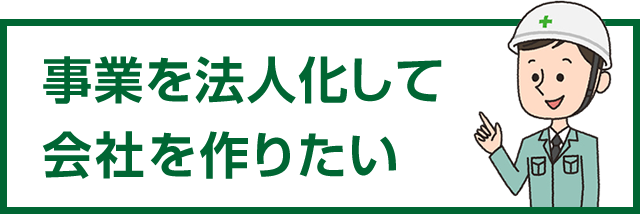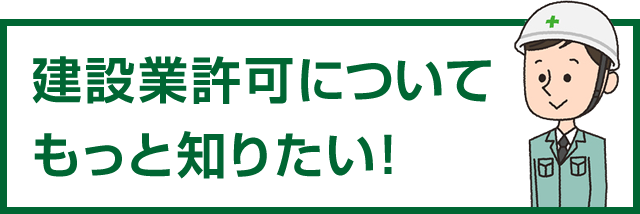- 個人事業主から会社を設立したけど、建設国保のままでよいの
- 営業所技術者等(専技)の実務経験期間中の常勤証明ってどうするの・・・
- 健康保険証に事業所名あれば、建設国保でも過去の常勤証明になるの・・・
公的な保険制度に加入していない個人事業主様や一人親方は、国民健康保険または建設国保に加入していなければなりません。
建設業の場合には、個人事業主様や一人親方の多くは建設国保に加入されているようです。
個人事業から法人化しても建設国保のままでよいの
でも、建設国保に加入している個人事業主様や一人親方が建設会社を設立した場合や常時使用する従業員の数が5人以上に増加した場合はどうなるのでしょうか。
何もしなくとも建設国保を継続できるのでしょうか。
実は、建設国保に加入している個人事業主様や一人親方が建設会社を設立した場合や常時使用する従業員の数が5人以上に増加した場合、社会保険の強制適用事業所になってしまうのです。
そのため、建設国保に加入している個人事業主様や一人親方は建設国保を脱退し、新たに健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入しなければならないのです。
<社会保険等加入義務一覧> 加入義務有=〇
| 区分 | 常用労働者数 | 健康・厚生 | 雇用 | 適用除外保険 |
| 法人事業所 | 1人~ | 〇 | 〇 | ― |
| 法人事業所 | 役員のみ等 | 〇 | ― | 雇用 |
| 個人事業所 | 5人~ | 〇 | 〇 | ― |
| 個人事業所 | 1人~4人 | ― | 〇 | 健康・厚生 |
| 個人事業所 | 一人親方等 | ― | ― | 健・厚・雇 |
でも、実際には、皆さんは法人化した建設会社様や常時5人以上の従業員を使用している事業者様が、建設国保に加入されているケースをご存知ですよね。
一体どういうことなのでしょうか。
建設国保で健康保険被保険者適用除外承認を受けるとどうなるの
なんと、個人事業主様や一人親方が建設会社を設立されても、年金事務所において「健康保険被保険者適用除外承認」を受ける等の必要な手続を済ませると、そのまま建設国保を継続できるのです。
また、常時使用する従業員が5人以上に増加した場合も、年金事務所において「健康保険被保険者適用除外承認」を受ける等の必要な手続を済ませると、そのまま建設国保を継続できるのです。
この制度は、他の産業にはない建設業独特の健康保険制度となっています。
つまり、建設国保に加入している個人事業主様や一人親方が会社を設立した場合や常時使用する従業員の数が5人以上に増加した場合でも、「健康保険適用除外承認」を受ける等の必要な手続を行い、建設国保の加入を継続させられるのです。
そのため、建設業においては、通常の健康保険制度では見ることのない、「建設国保+厚生年金保険被保険者」という事業者様が出てきます。
営業所技術者等(専技)の実務経験期間の常勤証明と健康保険被保険者証の関係ってなに(東京都の場合)
ここからが東京都の建設業許可に関係するお話しとなります。
東京都の場合、建設業許可の新規申請や業種追加申請等において、営業所技術者等(専任技術者(専技))の技術者要件が実務経験の場合、実務経験期間中の常勤を証明しなければなりません。
そして営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験を証明する場合、代表的な確認資料として健康保険被保険者証の写を挙げられます。
では、なぜ、東京都は営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験期間の証明に健康保険被保険者証の写を求めるのでしょうか。
それは、例えば協会けんぽや健康保険組合といった通常の健康保険の場合、営業所技術者等(専任技術者(専技))の健康保険被保険者証に記載されている資格取得年月日を確認することで、自動的に建設業許可の申請会社に入社した日を確認できます。
従って、営業所技術者等(専任技術者(専技))の健康保険被保険者証が現在も有効なものであれば、その資格取得年月日から現在まで営業所技術者等(専任技術者(専技))は申請会社に常勤で在籍していたことを確認できるのです。
建設国保の健康保険被保険者証で営業所技術者等(専技)の実務経験期間の常勤証明ってできるの
では、建設国保の場合にはどうなるのでしょうか。
実は、建設国保の場合、健康保険被保険者証に記載されている資格取得年月日は営業所技術者等(専任技術者(専技))が建設会社様に入社した日ではありません。
もちろん申請時点での営業所技術者等(専任技術者(専技))の建設会社様での常勤確認資料としては有効となります。
しかし、営業所技術者等(専任技術者(専技))が資格取得年月日から現在まで建設会社様に常勤で在籍していたことの確認資料にはならないのです。
どうしてなのでしょか。
建設国保の健康保険被保険者証で営業所技術者等(専技)の実務経験期間の常勤証明ができるか事例で確認してみよう
わかりやすく事例を用いて説明します。
東京都で内装リフォームを請け負っているAさんのケースです。
Aさんは、平成15年8月1日に以前勤めていた工務店を退職し、個人事業主として独立、同時に建設国保に加入されています。
その後、Aさんの堅実な仕事ぶりが施主様や工務店様に評価され、事業は拡大し、平成25年4月1日に事業を法人化、A株式会社を設立されます。
AさんはA株式会社を設立されましたが、建設国保を脱退されていません。
Aさんは年金事務所において「健康保険被保険者適用除外承認」を受ける等必要な手続を行い、厚生年金保険には加入されています。
このケースでは、Aさんの健康保険被保険者証には、資格取得日として平成15年8月1日、事業所名としてA株式会社と記載されます。
でも、Aさんは、平成15年8月1日からA株式会社に在籍していたわけではありません。
これこそが、建設国保と営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験証明の罠と言えます。
建設国保の場合には、健康保険被保険者証に事業所名が記載されていたとしても、過去の常勤性を証明するために他の確認資料を準備しなければならないのです。
例えば、東京都の場合には、厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が期間通年分記載されていること)の写、期間通年分の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)の写を準備しなければなりません。

建設国保と営業所技術者等(専技)の実務経験証明の罠(東京都の場合)
本記事では、建設国保の健康保険被保険者証は法人等における営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験期間中の常勤証明となるのか説明しております。
「建設国保+厚生年金保険被保険者」で、健康保険被保険者証に事業所名の記載があっても、それのみでは営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験期間中の常勤を証明することはできないのです。
<追加で必要となる確認資料(代表的な資料)>
- 厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が期間通年分記載されていること)の写
- 期間通年分の住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)の写
「建設国保+厚生年金被保険者」で営業所技術者等(専任技術者(専技))となられる場合、上記の点を十分に注意してください。
弊事務所では、東京都の建設業許可に関するお悩みの建設業者様からのご相談を積極的に承っております。
弊事務所は、東京都の建設業許可申請に関して、許可要件の確認から、証明書類の収集、申請書の作成と提出代行まで、手続を一貫サポートしております。
東京都の建設業許可でお困りの建設業者様、建設業専門の弊事務所に相談してみませんか。
※関連情報:健康保険被保険者証に代わる常勤性の確認について(東京都の場合)
令和6年12月2日以降、新たに健康保険被保険者証は発行されません。
それを受けて東京都は建設業の許可申請や変更届における常勤性の確認資料を変更しております。
この変更により、営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験期間中の常勤証明の確認書類についても注意を必要とします。
ここでは法人の場合について必要となる確認資料の概略をご説明します。
<法人の場合>
1 マイナ保険証(表面)・資格確認書・有効期限内の既存の健康保険被保険者証(事業所名のあるもの)の写のいずれか
2 1の確認資料に事業所名のない場合、1に加えて次の確認資料の写のいずれか(代表的な資料を抜粋)
・健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額通知書
・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票
※これらの確認資料も営業所技術者等(専任技術者(専技))の実務経験期間の期間通年分を必要としています。
行政書士に東京都の建設業許可申請を依頼する場合(ご参考)
行政書士に東京都の建設業許可申請(新規申請)をご依頼される際のご依頼の流れ・行政書士の料金・法定手数料等は、以下の通りとなっています。
ご依頼の流れ
東京都の建設業許可申請(新規申請)のご依頼の流れとなります。
| お客さま | お電話・メールにて相談(無料)をご予約ください。 |
| 行政書士 | 東京都の建設業許可申請(新規申請)のご相談をお受けいたします。 |
| お客さま | 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。 |
料金の目安
行政書士にて、東京都の建設業許可申請(新規申請)をサポート・代行させていただく際の料金目安となります。
| 許可の種類 | 許可区分 | 証明方法 | 報酬額目安(税抜) |
|---|---|---|---|
| 東京都知事許可 | 一般 | 営業所技術者が国家資格者 | 165,000円~ |
| 営業所技術者が実務経験者 | 200,000円~ | ||
| 特定 | 200,000円~ |
法定手数料・登録免許税など
行政書士の目安料金のほか、東京都の建設業許可申請(新規申請)ために必要となる諸費用となります。
| 許可の種類 | 法定手数料 | 登録免許税 | その他の実費 |
|---|---|---|---|
| 知事許可 | 90,000円 | - | 数千円程度 |
無料相談のお薦め
弊事務所では初回のご相談を出張相談でお受けしております。
もちろん弊事務所でのご相談も可能となっております。
いずれのご相談も初回相談は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。